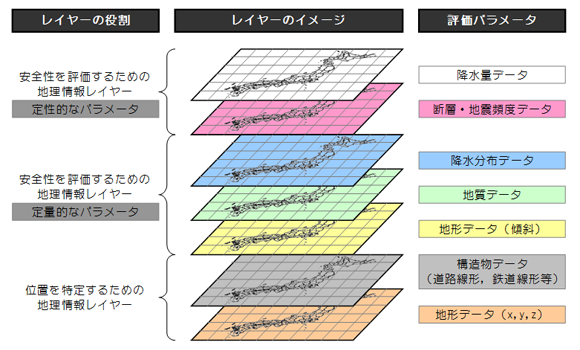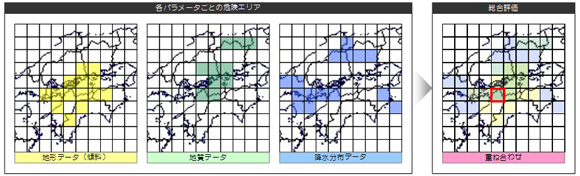少し前の話ですが、WindowsPhoneが発売されました。
http://www.microsoft.com/ja-jp/windowsphone/products/overview/default.aspx
スマートフォンの大手参入としては、iPhone,Android端末に続き第三の選択肢として期待されているようです。
しかしながら、このWindows Phoneは本当に普及するの?と、誰もが懐疑的に思っているのではないでしょうか?
個人的には現在のスマートフォン市場のシェアを覆すような爆発的な普及はないと思っています。
既にiPhoneとAndroid端末で市場が形成されていることは、スマートフォンに興味を持つ人の大半が知っている事実です。
iPhoneの特徴は、洗練されたデザインと快適な操作性を兼ね備えたブランド力と言えます。
一方、Android端末は、未成熟ながらも高機能、低価格、そして端末の選択肢が豊富にあることが特徴と言えます。
それでは、WindowsPhoneの他の端末にはない明確なメリットや魅力は何なのでしょうか?
それが、利用者側からも端末メーカー側からも見あたらないように思います。
今の、iPhoneとAndroid端末の関係は、1990年代頃のMacとPC/AT互換機(Windowsマシン)の関係と酷似していると思います。
すなわち、当時、Macは、デザイン性と操作性に優れ、また、画像や音を取り扱うことに特化していました。
キーボードなしでも操作できる操作性は、大胆で先進的だったと思います。
ちなみに、キーボードはオプション扱いでした。
一方、Windowsマシンは、事務的あるいは科学技術演算用といった感じで、文字・数字を扱うことに特化していたと言えます。今でこそマルチメディアにも対応できるWindowsですが、Windows3.1~95の頃はBASIC,FORTRANなどのプログラミングやワープロ・表計算といった用途で使われることが多かったのではないでしょうか。
それでは、Windowsマシンが普及した理由は何だったのでしょうか?
小生は、次の1点だっと考えます。
・IBMのPC/AT互換機で動作する。
つまり、PC本体の価格やソフトウェア上の互換性で市場を先に創ってしまったことにあると言えます。
この意味するところは、OSとしての機能を成熟させるよりも、普及させることを優先させたということに他なりません。
世の中に、PCが一般に普及した主な理由は、Webブラウジングと電子メールの存在といえます。
日本では、インターネット黎明期(1995年~)には既にNECのPC-9800シリーズというPC/AT互換機ではないPCが存在していました。
海外ではIBMのPC/AT互換機、日本では、このPC-9800シリーズがWindowsOSを採用していたことが世の中にWindowsの普及に大きく貢献したと思います。
1995年頃に、Macがどんなに優れたPCだったとしても、近くで使っていた人を小生は知りません。
当時、PCを購入したい人に「MacとWindowsだったらどっちがいいの?」と訊かれると、
「インターネットやメールだけならどっちでもいいよ。でも、困った時に、Windowsの方が他に訊ける人が多いよ…」
と、あるいは、「一太郎やExcelを使いたいならWindowsに…」と言われた方もいらっしゃると思います。
これと近いこと、あるいは同じことが、今、スマートフォンで起きているのだと思います。
つまり、Android端末は、ver1.*の頃は、iPhoneには明らかに操作性が劣っていました。
しかしながら、Android端末は、端末メーカーが無償で利用できること、iPhoneではサポートされていないFlashコンテンツが閲覧できるということで、急速に普及してきました。
現在のバージョン(スマートフォン:ver.2.3,タブレット:ver.3.1)になって、機能的に落ち着いたてきた感じはありますが、まだまだ進化を続けている過程にあると言えそうです。
この機能的に落ち着いてきた感じがあるのは、普及台数が増えることで、改善点が早期に発見できたことと、市場が確立されることによって、改修にかかる費用が(Googleの)経営上の負担にならないということが大きな要因になっているのだと思います。
それでは、PCの世界ではMacOSとWindows以外のOSはないのでしょうか?
そんなことはありません。
LinuxやFreeBSDSといった他のOSもあります。BeOSというのもありました。
しかしながら、Linux系のOSを除いては、世の中に浸透しているとは言い難いのが現状です。Linuxもサーバーでの使用率は高いですが、一般にはあまり浸透していないといえます。(今のMacOSがLinuxベース(?)であることは除きます)
つまり、成熟した市場でのプラットホームビジネスは、新規参入が難しいということを示唆しているのだと思います。
PC用Windowsとの親和性からすると、個人的にはWindowsPhoneに頑張って欲しいと思うけど、「買うか?}と訊かれたら、現時点では「買わない」と答えます。
ドコモで販売されたら検討対象にはなりますが…